「育休」ではなく、男性版「産休」が新設!
はじめに
令和3年6月3日、男性も子育てのために休みを取りやすくする「改正育児・介護休業法」が衆院本会議で可決され、成立しました。
「改正育児・休業法」は令和4年度中にも施行される予定です。

この改正によって、男性版「産休」制度が新設されました。
では、新設された男性版「産休」とは、どのような制度なのか見ていきましょう。
そもそも育休制度とはー労働者が申請して雇用主が承認するもの
その前提として、現行の育休制度を少し振り返ってみましょう。
まず育児休業は、労働者が法定の要件を満たして申請をした場合、事業主は拒否できないものとして規定されています。
このことから、育児休業の権利は、
- ① 法定の要件を満たす労働者の一方的な意思表示によって
- ② 休業という効果、つまり労働義務の消滅を発生させる形成権
また、育児休業の権利は強行的な権利であり、これに反する合意をしたとしても無効とされます。

仮に就業規則等に育児休業の権利を認める規定がない場合であっても、育児・介護休業法の規定から直接権利が発生する法律上の権利であるとされています。
そのため、使用者が労働者による育児休業の申請を拒否し、育児をしながら就労せざるを得なかったことについて、不法行為として損害賠償を命じた裁判例もあります(東京高判平成17年1月26日労判890号18頁)。
育児休業は以上のような法的性質のものになります。
現行の制度
そして、現行の育休制度を簡単に説明しますと、以下のようなものになっています。

現行の育児・介護休業法の概要
- 子が1歳(保育所に入所できないなど、一定の場合には最長2歳)に達するまでの育児休業の権利を保障。
- 父母がともに育児休業を取得する場合には、子が1歳2か月に達するまでの間の1年間取得できる(パパ・ママ育休プラス)。
- 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度の育児休業の取得が可能(パパ休暇)。
- 休業中、賃金の支払義務なし。
※ただし育児休業給付金(賃金の67%又は50%)あり。 - 事業主が、育児休業を取得したこと等を理由として解雇その他の不利益な取り扱いをすることを禁止。
- 事業主に、上司・同僚等からの育児休業等に関するハラスメント防止措置を講じることを義務付け。
しかし、男性の育休取得率は非常に低い
現行の育休制度は以上のとおりですが、次に見るとおり、育休制度はあっても、男性の取得率は高いものではありませんでした。

現育児休業取得率
| 年度 | 女性(%) | 男性(%) |
|---|---|---|
| 2009年 | 85.6 | 1.7 |
| 2010年 | 83.7 | 1.4 |
| 2011年 | 87.8 | 2.6 |
| 2012年 | 83.6 | 1.9 |
| 2013年 | 83.0 | 2.0 |
| 2014年 | 86.6 | 2.3 |
| 2015年 | 81.5 | 2.7 |
| 2016年 | 81.8 | 3.2 |
| 2017年 | 83.2 | 5.1 |
| 2018年 | 82.2 | 6.2 |
| 2019年 | 83.0 | 7.5 |
※出典元:厚生労働省「雇用均等基本調査」
※調査前年度1年間の出産者(男性の場合は配偶者が出産した者)の数のうち、調査時点までに育児休業を開始した者(開始予定の申出をしている者を含む)の数。
※2011年度は、岩手県、宮城県、福島県を除く全国の結果。
厚生労働省の調査によると、男性の育休取得率が年々増加傾向にあり、2019年度には過去最高の7.5%に達しました。
しかしながら、女性の育休取得率と比較すると、依然として低い水準にあり、男性の育休取得にはまだまだ課題が山積していました。
改正育児・介護休業法によって、男性も取得しやすくなりました。
このような状況の中、男性も子育てのための休みを取得しやすくするために、育児・介護休業法が改正されました。
改正内容を簡単に説明すると、以下のとおりになります。
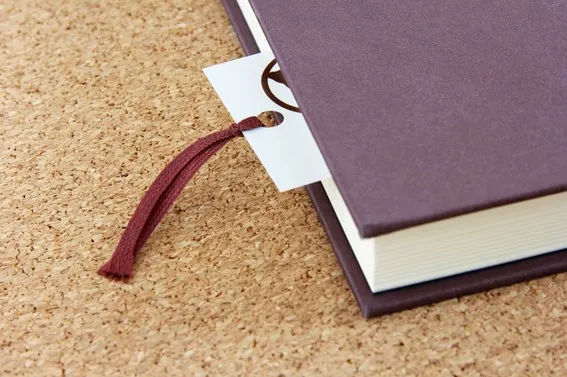
改正育児・介護休業法
- ① 男性版「産休」を新設し、生後8週間以内に4週間まで2回に分けて「産休」を取得できる。
- ② 原則1回の通常の育休を、男女ともに2回まで分割取得が可能となる。
- ③ パートなど有期契約労働者の取得要件を撤廃。
- ④ 企業に産休や育休の取得意向の確認を義務付ける。
- ⑤ 従業員1000人超の企業に、取得状況の公表を義務付ける。
以上のように、改正によって①
男性版「産休」制度が新設されました。
では、なぜこのような男性版「産休」制度が新設されたのでしょうか?
「育休」は申請時期や、変更に制限があって、取りにくかった。
これまでの育児・介護休業法においても、男性はパートナーの出産により、原則として子が1歳に達するまで「育休」を取得することができました。
しかしながら、この「育休」は、原則として育児休業開始予定日の1ヵ月前までに申請しなければならず、その変更申請も1回に限られていました。
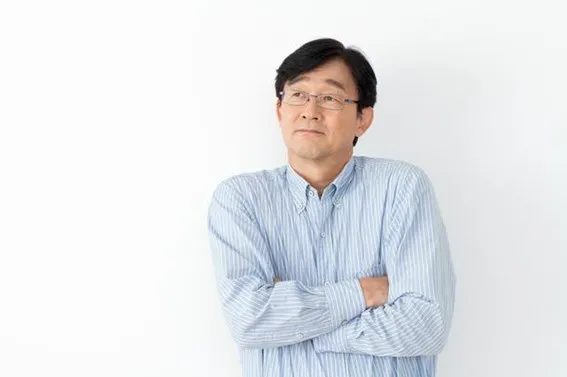
他方、出産予定日の6週間前から出産後8週間まで取得できる「産休」は、女性だけが取得できるもので、男性には認められていませんでした。
そのため、「産休」がない男性は、出産日が早まった場合には、
「子が生まれているのに育休に入れない」という問題が生じていました。
男性の育休取得時期が子の出生後8週間以内に集中していることを踏まえると、このようなタイムラグは決して望ましいものではありませんでした。
男性も「産休」取得可能に。企業側にも確認義務などを追加
そこで、現行制度での育休取得状況や女性の「産休」を踏まえ、男性も子どもの出生後8週間以内に、4週間まで2回に分けて男性版「産休」を取得できるようにしました。
またその他にも、③これまで有期契約労働者の取得条件とされていた「1年以上の継続雇用」を廃止し、非正規社員でも育休を取得しやすくしました。
企業側には、④従業員に対して産休・育休の取得意向を確認するよう義務付け、また⑤従業員が1000人を超える企業には育休取得率の公表を義務付けました。

これは、これまで日本が育休制度を整えたとしても、職場の慣習や雰囲気から取得にためらう男性が多かったためです。
これにより、「育休が取得しづらい雰囲気」を変え、企業が取得を促すような仕組みを整備しました。
企業側も環境を整備することでメリットがあります。
以上のように、今回の育児・介護休業法の改正では男性版「産休」制度が新設されるとともに、企業としても男性が育休等を取得しやすくなるような職場環境の整備が義務付けられました。
もっとも、労働者に育休等を取得させる義務まではなく、実際に育休等を取得するかどうかの判断は、あくまで労働者に委ねられています。
ただし、企業としては、労働者が育休等の取得を前向きに検討できるような職場環境を整備するとともに、労働者から申請があった場合には、これを拒むことはないようにしましょう。

労働者の育休取得を促進することで、企業のイメージアップが期待できるばかりでなく、両立支援等助成金の「出生時両立支援コース」という、助成金を受給することができるなど、企業としてもメリットがあります。
日本の少子化に歯止めをかけ、女性が出産後も就労を継続できるようにするためにも、男性が育休等を取得するなど、積極的に育児に参加していくことが重要であるかと思います。